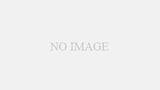今回の記事では、津軽三味線を弾くときに必要な基本の道具をざっと紹介します。
①三味線本体(太棹)
基本的には木製です。花梨、紅木、紫檀など、いくつか材質に種類があります。材質によって音質や値段、重量などが異なります。一般的には皮に犬皮が使われています。
近年、人工皮やアクリル製の三味線なども出てきています。
物によっては、棹を3つに折り畳めます。折り畳んだ時は、継ぎ目のところに仮継ぎという木製のパーツをはめることで、折れたり欠けたりするのを防ぎます。
糸巻きも同様に、黒檀、象牙、プラスチックなど、異なる材質のものがいくつかあります。
通常、三味線の天神にはキャップ状のカバーをつけて、胴には胴掛けを掛けます。また、側面下部の体に乗せる部分にはゴム製の滑り止めのシートを貼ります。また、皮の中央(の上部)で弦が張られている部分の真下ある部分には保護用のバチ皮シール(プラスチック製)を貼ります。
②バチ
持ち手の部分は、プラスチック、水牛、象牙、木など様々な材質があります。持ち手のあたりに鉛などを入れて重量を調整しているものもあります。持ち手の厚さや長さ、幅、バチの先端の厚みや開き具合など、様々なものがあります。持ち歩く際に先端が欠けないようバチ鞘をつけて、バチ入れに入れます。バチ先が欠けてきたら、細目の紙やすりで少し磨くと、絃が傷みにくいです。
③駒
三味線の絃に高さをつけて、音を鳴らすのに必要なパーツです。台の部分は木や竹で、絃に触れる部分は牛骨や鼈甲などでできています。
音緒から指3本分くらいの距離の場所に挟みます。
駒の高さによって微妙に音や弾きやすさなどが変わります。2分5厘、6厘、7厘、8厘くらいまで、高さに幅があるので、自分の使いやすい高さを確かめてみると良いです。
室内練習で音量を抑えたい時向けの、忍び駒という道具もあります。
駒は湿気で少し曲がることがあるので、桐の小箱などに入れておくと良いです。
④絃(糸)
1番太い1の糸、中間の2の糸、最も細いのが3の糸です。1の糸と2の糸は絹糸、2の糸はテトロンの糸も存在します。3の糸はナイロン製が一般的です。絹糸は音が良く、テトロン糸は丈夫です。津軽三味線用でも、若干太さなどに幅があります。
⑤指掛け
左手の親指と人差し指に装着する、毛糸で編まれた物です。大きさや色、デザインなど様々なものがあります。編み物が得意な方は自作できるかもしれません。練習頻度によりますが、3日から1週間に1回は洗濯すると良いです。
⑥ツヤ布巾
三味線の棹や撥などを拭くための布です。こちらも、練習頻度によりますが、3日から1週間に1回は洗濯したほうが、棹の汚れを取りやすいです。また、色が薄めのものを選ぶと、汚れ具合などわかりやすいです。
⑦調子笛/チューナー
調子笛は、合わせたい音程の部分を吹いて音を出しながら、自分の三味線の絃の音程を合わせるのに使います。
チューナーは、鳴らしたい音程と自分の出しているの音程のズレを可視化して、音程を合わせるのに使います。
⑧三味線ケース
三味線をしまっておくケースです。長いまましまえるもの、折りたたんでしまうもの袋状のもの、箱型のものなどいくつかあります。頻繁に練習する場合は長いまま収納できるケースが便利です。箱から出して駒をセットして調弦すればすぐ弾けます。移動して使う際には3つに折り畳んで持ち歩くケースも便利です。
⑨三味線を入れる布袋
こちらも、長袋と、三つ折り用の袋があります。胴の部分は、この袋に入れる前に和紙袋とビニール袋に重ねて入れると、湿気などの影響を多少軽減できます。
以上、今回は津軽三味線を弾く時に必要な基本的な道具を紹介しました。
近々の記事で、練習時の便利アイテムなどを少しまとめて紹介できればと思います。