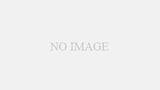もうすぐ梅雨に入りますね。
湿気が高まり、津軽三味線の皮が破れる時期がやってきました。
そもそも人工皮を使えば、皮が破れる可能性はかなり下がるらしいです。いつか試してみたいです。
今回は犬皮の津軽三味線で、少しでも皮が破れる可能性を下げるために普段できること(?)を書きます。
- 三味線を保管する時、窓際に置かない
- 乾燥剤を入れる(楓音ぶくろ、雅など)
- 胴と糸の間に桐の板に挟む
- 長袋(胴袋)の胴の付け根付近の紐をしっかり縛る。
- 練習の際に、三味線の胴と自分の腹の間にタオルを1枚挟む
- 練習後に皮付近もさっとツヤ布巾で拭く
- 撥皮シールに皺が寄ってきたらこまめに張り替える
- なるべく毎日弾くようにする
- 三味線を保管する時、窓際に置かない。
窓際付近は、室内外の境界ともあり、温度変化が大きいです。
また、暖かく湿った空気がひんやりした窓ガラスに触れて結露が生じます。
なるべく窓際付近に三味線を置くのは避けましょう。 - 乾燥剤を入れる(楓音ぶくろ、雅など)
楓音ぶくろは緑色の袋に入った乾燥剤です。
胴に直接付けず、胴から少し離れた棹の付近に入れて使います。
雅は、薄型で、三味線の胴の両側に入れる構造になっています。
私は皮に直接つけずに、和紙袋を2枚重ねにして、1枚目と2枚目の紙袋の間に入れて、その上からビニール袋を掛けて使っています。
乾燥剤には使用期限があるので、(梅雨時期だけでも)なるべく守りましょう。 - 皮と絃の間に桐板に挟む
桐板は湿気に強く防虫効果があり、熱伝導性も低い材です。
和服などを保管する箱にも使われています。
三味線の皮に挟む用途の薄い桐板も和楽器屋などで販売しています。 - 長袋(胴袋)の胴の付け根付近の紐をしっかり縛る。
縛りが緩いと湿気などの影響で破れるリスクが高まるので、しっかりと縛りましょう。 - 練習の際に、三味線の胴と自分の腹の間にタオルを1枚挟む
特に暑い時期に普通にTシャツなどを着て練習していると、汗をかいて三味線と腹の間らへんに湿気がこもることがあります。タオルを1枚挟むと、湿気を吸ってくれます。
弾いている間にタオルが動く場合は、着物の着付けなどに使う紐で縛っておくと多少ずれにくくなります。 - 練習後に皮付近もさっとツヤ布巾で拭く
皮をすごくゴシゴシ拭く必要はないですが、棹、撥、糸巻きだけでなく、5で書いたように湿気がこもったりする場合もあるので、皮もさっと拭いてから袋にしまいます。 - 撥皮シールに皺が寄ってきたらこまめに張り替える
これはあまり梅雨の湿気と関係ないかもしれません。
ただ、小さい傷のところからパックリ皮が破れたりすることもあるので書きます。
撥皮シールに皺が寄ってきたら、小さい穴が開く前に張り替えた方が、皮にダメージがいきにくいです。張り替える時、貼る部分に軽く蝋を塗ってから貼ると、次張り替えた時剥がしやすいです。私は仏壇用の小さな蝋燭を塗って、塗り終わって張り替えたらツヤ布巾で軽く拭いてます。 - なるべく毎日三味線を袋から出すようにする
これは、三味線の皮の状態確認も兼ねています。
いざ練習しようとして皮が破けていたら、切ないです。
また、皮が破れた状態で三味線を長く放置すると胴板同士の繋ぎ目がゆるくなります。
なるべく早く発見して修理に出せるよう、こまめに確認しましょう。
少し長くなりましたが、今回の記事は以上です。
皆様、くれぐれも湿気にお気をつけ下さい。