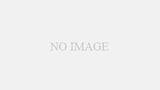津軽三味線の演奏は、撥で強く叩く奏法が一般的です。ハマると楽しいので、がっつり練習したくなる時もありますが、負荷のかかるフォームで長時間練習してしまうと、手首を痛めてしまう場合があります。
私もおおよそ3年ほど前に手首に痛みを感じ、整形外科を受診した際に腱鞘炎と診断されたことがあります。当時はフォームをあまり気にせず、週5日程度で2時間以上休憩せずに、毎回同じようなやり方でがっつり叩き続けるような練習をしていたと記憶しています。もっと練習しても手首を痛めない人もいると思いますが、腱鞘炎を1回経験してから、少し気をつけるようになりました。
幸い現在は、特に腱鞘炎を再発せずに津軽三味線を続けられています。
というわけで、今回は腱鞘炎対策と発症時の対処について少しだけ書きます。
⭐︎予防
①練習時間と休憩時間を把握
キッチンタイマーで管理すると早いです。私は、近所の病院の理学療法士さんの助言を参考に、連続して30分ほど弾いた際に5分間は休憩を取るようにしています。
また、練習時間を手帳(カレンダー)に記録して管理しています。
②練習前後や休憩時間のストレッチ
パソコン作業やデスクワークとも通じるところがありますが、同じ姿勢で長時間反復動作をしていると、筋肉が凝ってきます。これを少し緩和するために、短時間でもストレッチや軽い運動をします。
特に、肩や首周りを少し回して伸ばしたり、手首を少し回したり伸ばしたりします。
③定期的にフォームを確認し、必要に応じて修正を心がける
姿見(鏡)を使ったり、たまに三脚を用いて演奏を動画撮影してみたりして、自分の演奏姿勢の癖を確認して、修正を試みます。肩や腕などに無駄に力が入ったり、前かがみになったり、必死に弾いていると姿勢に癖が出てしまう場合があります。
これを把握して修正するよう心がけると、多少は負荷が少ないフォームに近づけます。
⭐︎発症したら
①1週間などまとまった時間、(撥を使って叩くような)練習を休む
腱鞘炎は怪我の1つです。怪我を治すときは、怪我した部分をなるべく使わず休ませる必要があります。この期間になるべく余裕があれば整形外科などを受診すると、症状に応じて痛み止めや湿布などを処方してもらえる場合があります。特に初めて腱鞘炎を発症し、対処法がわからない場合には、練習を中断する期間について、医師に助言を求めて判断する方が良いかもしれません。
②痛いかも、という感覚をちゃんと把握する
腱鞘炎の始まりは、少し手が痛いかなー、重いかなー、という違和感から。
自分で手首や腕の状況を把握して練習を加減することができないと、悪化の原因になります。長く津軽三味線を楽しめるように、練習が乗ってても、手の状態が良くない際には、少し休めたり冷やしたりしたほうが良い場合もあります。
手が重いかな?と感じた時点で数分休憩を入れるだけでも、腱鞘炎になるリスクを緩和できます。集中していると続けて弾きたくなりますが、何か音源でも聴いて、休憩中は弾くのを我慢してみてください。
③弾けない時の練習
ありきたりですが、腱鞘炎でバチを使った練習ができない時に、代替でできる練習方法を紹介します。
音源を聴く・練習の動画を見る→他の奏者の弾き方を確認したり、今まで稽古などで自分で録音した音源などを振り返ったりすることも、練習に役立ちます。
どうしても三味線に触って練習したい場合には、バチを握らずに、つまびきで練習すれば、手首にかかる負荷は軽減できます。親指・人差し指の腹のあたりで絃を弾きながら、左手の動きや、間の取り方などを確認してさらう練習です。バチを使う練習よりも音が出ないので、音源を聴きながらつまびきするのも一つの練習手段になります。
津軽三味線を長く楽しむためにも、腕や手首の状態をたまに気にかけてみると良いかもしれません。